ヒグマ春夫の映像パラダイムシフト

2016年2月24日/九十九里浜海岸


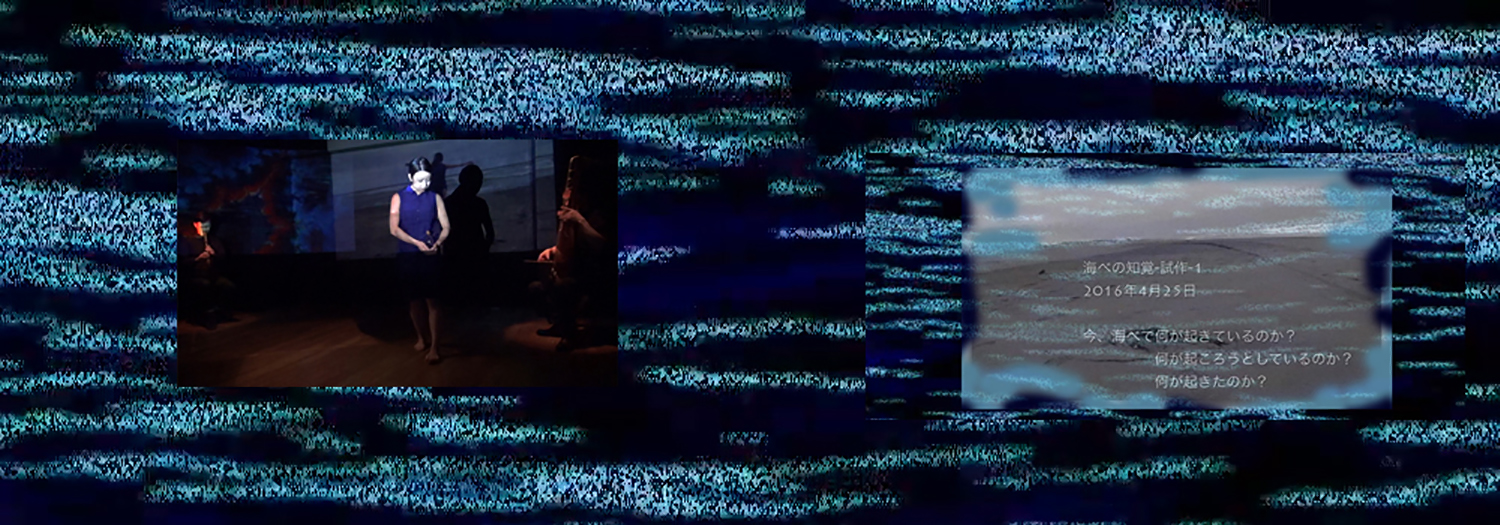
報告:宮田徹也(日本近代美術思想史研究)
舞台には何もない。右奥に琵琶のみが置かれている。ヒグマは客席前方右側に席を用意している。後方壁面左に映像が投影される。サイケデリックなCGが渦巻く中、中央から小窓が出現し、草原の中の家の写真が徐々に拡大される。
水面の加工した実写映像に変わり、奏者二人が入場する。後方壁面右にも映像が投影される。モノクロの風景の動画である。極端なスローモーションが、写真と誤認させる。道とも海とも見える映像が持つ雰囲気は、映像が持つ確固たる力を感じさせる。
「海べの知覚・試作-1/2016年4月25日/今、海べで何が起きているか?/何が起ころうとしているか?/何が起きたのか?」という白抜きのテロップが流れる。海辺をあえて「海べ」としていることによって、身近な印象を見る者に与える。
我々は海辺で何が起きているか、知る由もない。それによって何が起こってしまうのか、未来を予兆できない。何が起きたのかという真実も知らされていない。微かな不安を想起しても、何もすることができない。しかし、考えることによって何かが変わる。
塩高は琵琶の弦を撥でスクラッチする。塩高は伝統技法に長けているからこそ、琵琶をギターのように独自の方法で演奏し、ロックやフリージャズ、現代音楽のような要素を散りばめていく。それに応える琵琶という楽器の屈強さに私は感銘を受ける。
後方壁面右には公園の写真が中央から拡大され、下の色面を覆い隠す。田中が尺八により息吹を放つ。右の写真は小さくなって消える。代わりに小松のダンスの実写動画となる。小松は砂に爪先で線を描いていく。

田中の尺八によって描かれた水墨画的風景に、塩高の放つ雷電のようなパルスが唸りを上げる。音楽が映像的であると感じるのは、映像が物語のような音楽性を帯びていることに由来する。映像はCGという無機と海辺の有機が入り混じる。
塩高は撥を使い分け、琵琶に対してアタックに強弱を交える。田中の尺八が止まる。塩高は、自らが形成した静謐なフレーズを喧噪的に破壊する演奏を繰り返す。後方壁面の右の実写動画は早送りで、左の水面的CGには横の波線二本が横切る。
恐らくヒグマはライブで映像の速度をコントロールしているのであろう。右の映像は従来の速度に戻る。映像の小松は両手を広げる。左の映像は家庭の物置場の写真が色面の上で拡大しては縮小する。
突如、小松が舞台に上がる。右の実写動画と同じワンピースを着ている。小松は水が入った透明なボトルを手に持っている。塩高は撥の背で琵琶のブリッジを規則的に叩く。再開した田中の尺八は、謡とも語りにも聴こえるフレーズを操る。
小松は後方壁面から前に向かい、右掌でボトルの底を押し、左上腕部から肩、首筋へとボトルを移動させる。右掌を上、つまりボトルを逆さまにして腹部付近に支える。塩高と田中はまるでJ・コルトレーンの《アセンション》のような演奏となる。
後方壁面の左の映像は、室内で握り締められたボトルの写真が色面の上に拡大されては縮小する。左の実写動画はスローモーションで投影される。実体の小松は舞台中央にボトルを置く。塩高と田中の演奏に秩序が生れる。

小松の爪先が交互に床を撫でる。塩高の琵琶はノアの箱舟を誘った洪水のように唸りを上げる。田中の尺八は、降り頻る雨を連想させる。しかし二人の演奏は決して情景的ではなく、象徴的である。
小松は四足で、床にあるボトルに干渉する展開となる。右の実写録画はコマ送り、左のCGは水面のみとなる。田中の尺八が止まると小松は立ち上がりゆっくりと舞台を巡る。ヒグマは後方壁面右の実写動画を自己の位置にある赤外線カメラからのライブに切り替える。
小松がプロジェクターを横切る度に生れる影が美しい。小松は旋廻し、テンポを落とした霧のような琵琶と風の如き尺八の間を縫っていく。演奏のビートが激しくなる。後方壁面左は家族写真が拡大されては縮小され、右は実写動画に戻る。
小松は頭部を壁面につけて揺らぎ、倒れる。中央のボトルに薄く照明が当たり、小松は近づく。小松はボトルの蓋を開け、右手に中の水を掬って口に含む。腕と足に水を塗り、蓋をして逆さに床へ置く。
二人は音を空間に染み込ませていく。小松は客席を向き、髪を解き、両手を大きく広げる。腕を大きく振りながら踊る。塩高はスクラッチしつつ低い声で尺八のフレーズを歌う。映像はボトルの水、水面、CGの水のイメージと多様に展開する。
映像は淡々と続く。小松は後方壁面で沈黙する。映像が潰え、演奏が終ると小松が客席に背を向け、公演は終了する。静寂でありながらも滾々と湧き出す水が炎のように燃え盛った劇的な55分間であった。

4月25日(月)明大前キッド1Fホールにて、琵琶奏者の塩高和之さんをゲストに迎えた「ビグマ春夫の映像パラダイムシフト vol.77」を観劇。事前のクレジットはありませんでしたが、公演の内容は、映像と琵琶演奏の即興的なコラボではなく、演奏方ではもうひとり尺八の田中黎山さんが加わり、さらに映像のなかに登場するダンスの小松睦さんが参加する形で、9月の<ACKid2016>で公演される「フラクタルライン・海べの知覚」に向けての実験的かつクリエーション作業的公演「海べの知覚・試作-1」となりました。「海べの知覚」のテーマは、「東日本大震災で太平洋側の海岸線は、甚大な被害を受けた。あれから5年の歳月が経った。その海べの知覚は、どのように変化したのか。そして現在どんな状態にあるのか。海べに身を置き、海べの知覚を感じ表現することで、そこに出会ったことのない未知の人たちに伝える試み」とのこと。映像は二種類が用意され、下手のコーナーには、水面、水が半分入ったボトル、赤、青、緑の原色で影をつけられたフラクタル模様などが、また正面のホリゾント壁には、ダンサー小松睦さんがいる曇天の日の海べの風景が投影され、「海べの知覚・試作-1/2016年4月25日/今、海べで何が起きているか?/何が起ころうとしているか?/何が起きたのか?」の文字がインサートされました。

これまで映像展に登場した、人気のない、ものさびしい海岸線の風景には、公演直前の撮影であることを示す日付のクレジットが付されていたのですが、これは映像作家にとって、東日本大震災や原発の過酷事故が、なによりも経過していく、あるいは更新されていく時間の問題であることを示しています。あらためて見ると「海べの知覚」には(少なくとも)3つの時間が重ねられているようです。ひとつは地震や津波の自然災害による変化(あるいは災害からの回復過程)、もうひとつは放射能のうち大気中に大量に放出されたセシウム137の半減期が30年に及ぶという人為災害による環境の変化(あるいは被曝による遺伝子切断という不可視の身体的事件)、そしてそれらの時間を超え出てゆく、私たちの意識にはとらえることのできない生成変化しつづける自然の永遠性で、これらの時間が、災害を直接映し出すことのない「海べ」の風景に折り重ねられたところに、スタニスワフ・レム『ソラリスの陽のもとに』(1961年)の神秘性、J.G.バラード『溺れた巨人』(1971年)の災厄性、ミシェル・セール『生成』(1982年)の複雑系など、「海べ」のイメージの歴史が喚起されてきます。例えば、水面の映像に重ねられたフラクタル図形は、生成変化をやめることのないセールの「海べ」につながるものでしょう。
風景としての「海べ」は、具体的な撮影の日付をもつことでイメージの歴史から切り離され、観客の前に引き出されてくるのですが、そればかりでなく、さらに積極的に、映像のなかで踊るダンサーと映像の外で(ライヴで)踊るダンサーのシンクロナイズする身体を介して、観客を生々しい感覚をともなう “この” 砂浜のただなかに引き出します。すなわち、映像に登場する水の入ったボトルと同じ形のものを両手に大切そうに持って登場した小松睦さんは、ボトルをそっと床に置いてその周囲を回ると、腰をおろして水をすくい、オイルを塗るようにして腕をさすり、足についた砂を軽くはらうことで、会場を砂浜へと変貌させたのでした。いつものようにオブジェも置かず、上手下手に用意された椅子にミュージシャンが座っただけの会場は、中央に広く開いたスペースが(映像投影のない)身体のための幻想空間になったのでした。ヒグマさんの映像操作によってふたつの身体は差別化され、砂浜を動く映像の小松さんは、ある瞬間にはスローモーションで、またある瞬間には高速度で動く機械的処理を施され、動きの日常性を剥奪されていました。最後に、ステージの奥からセンターに這って出てきた小松さんが、ボトルのふたを開け、水を飲み、足を濡らす場面は、「海べ」に対する私たちの感覚をいっそう鋭くするものだったと思います。
このところ映像展の常連となっている小松睦さんのダンスは、二種類のスクリーンの枠内に入ったり、プロジェクターの前に立って映像にヒトカタの影を投げたり、尺八奏者のうしろを抜けて下手の柱の暗闇に張りついたり、特に、砂まみれになって横たわるダンサーをカメラがクローズアップする映像の終盤では、砂浜にいる自分と似た姿勢で床を前後に動いたりするなど、映像をダンス譜としても使いながら、ステージに交錯する光のどこに身を置けば踊りが展開するかを知り抜いた、みごとに個性的なものだったと思います。なかでも、前半の舞うような動きから、ジャンプし回転するダンスへの転調(あるいは破調)を見せた場面で、琵琶と尺八によるホリゾンタルな音の動きに沿う舞いの形から、違和的な身体が立ちあらわれてくるスリリングな時間帯は、ことのほか印象的なものでした。映像、音楽、身体のどれも欠くことのできない公演のなかで、この晩のダンス・パフォーマンスは、映像の可能性を開こうとするシリーズ公演が、「海べの知覚」になぜ身体の参加を求めているかを実感させたという意味で、大きな達成であり成果だったと思います。
塩高和之さんの琵琶と田中黎山さんの尺八による即興アンサンブルは、東日本大震災以後の感覚の変容を「海べ」において意識化しようとする本公演において、聴き手の感情をかきたて、出来事を内面から立ちあげるという重要な役割を担っていたように思います。終盤で尺八が声を使う場面がありましたが、そこに言葉はなく、響きを際立たせるだけで堅固な形式をもたないホリゾンタルな演奏のありようは、映像が映し出す海岸線や、(想像の砂浜を)水平に動いていくダンサーの身体とシンクロするものでした。とはいえ、強度のある響きは、それが怒りの感情なのか絶望の感情なのか語られることのないまま、おそらくは他でもない聴き手の内面を反映することになるのだと思います。曇天のした、映像のなかで波が打ち寄せる灰色の海べに立ち、強風に衣装をたなびかせながら全身で世界を受けとめるダンサーの姿は、踊るともなく、すでになにかを予兆しているようでした。(福島県出身のドラマー長沢哲さんが早くから語られていたヴィジョンを参照すれば)「海べの知覚」は変化したのではなく、私たちはすでに崩壊感覚のなかにあり、残された断片からもう一度風景を再構成しなくてはならないということではないでしょうか。■